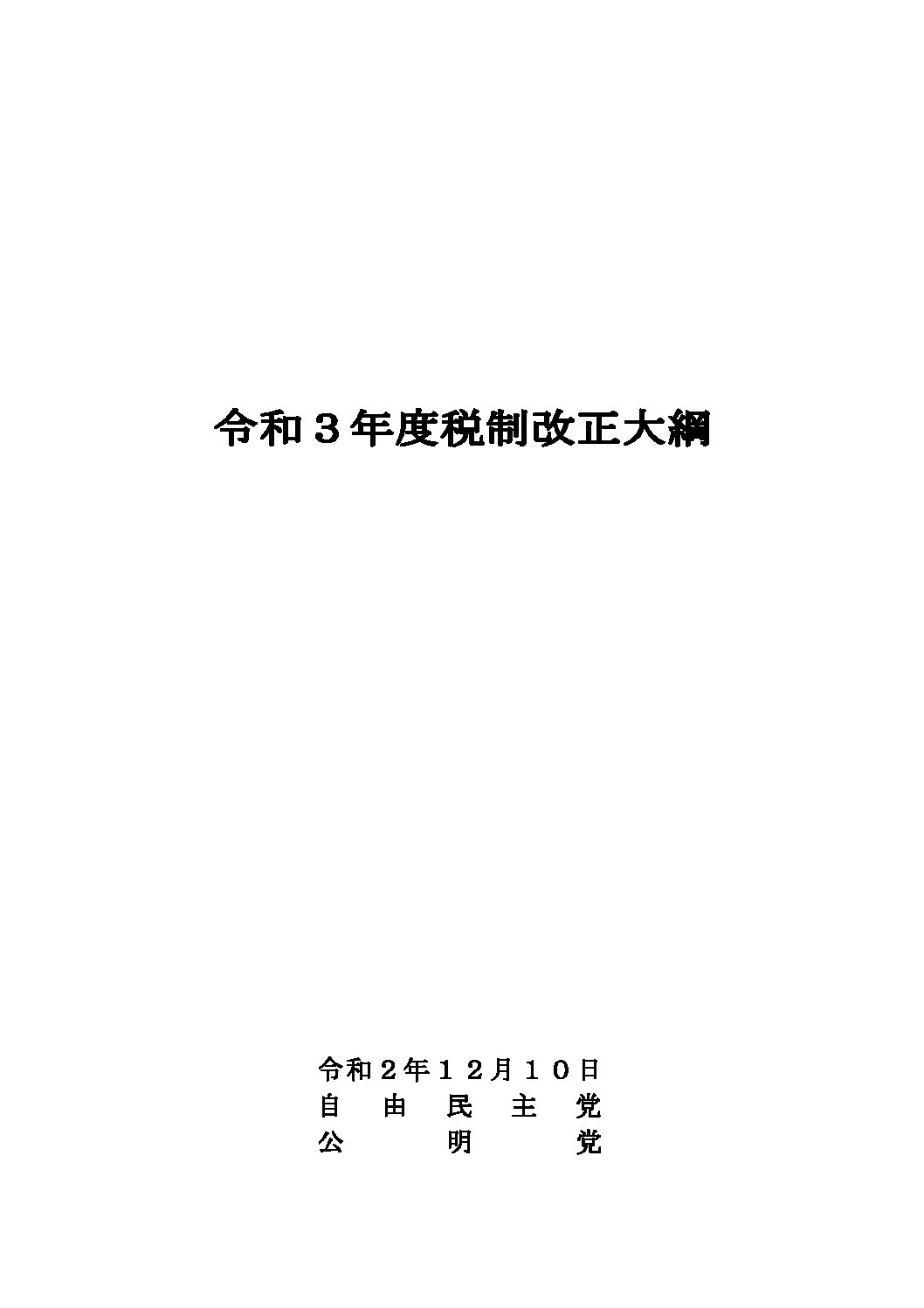生前贈与が税制改正でお得になり「相続時精算課税制度」を使うべき4つの理由!
週間ダイヤモンドによると、2024年5月、国税庁は2023年分の贈与税の確定申告状況について公表しました。
報道向けの発表資料によると、贈与税申告書の提出者は51万人に上り、前年よりも2.6%増加しています。
51万人のうち、申告納税額があった方は37万6,000人と、こちらは前年比より0.9%減少しています。
同資料では、贈与税の課税方法についても公表しており、暦年課税を適用した人は46万1,000人(前年比1.5%増)、相続時精算課税を適用した人は4万9,000人(同13.3%増)となっています。
いずれの贈与方法も前年より伸びていますが、特に注目すべきは「相続時精算課税制度」です。
これまで「使いにくい」とも言われていた相続時精算課税制度ですが、高い伸び率であり、今年は法改正もあったことから、さらに注目が高まっています。
では、本制度を使うべき理由とはどのようなものなのでしょうか?
今回の記事では、2024年最新版の情報に触れながら、相続時精算課税制度を使うべき4つの理由を紹介しています。
2024年は「相続時精算課税制度」に法改正があったことはご存じでしょうか?
今回の改正により、新たに非課税枠が新設されたのです。
元々本制度は2,500万円までの生前贈与なら贈与税がかからない(特別控除)しくみであり、贈与者が死亡した際に相続財産に持ち戻しをして、相続税計算を行うものです。
なお、暦年贈与と併用することはできません。
例えば、母親が子に対して生前に本制度を使って2,500万円の贈与を行い、母親の死去後に遺産が1億円あったと仮定します。
この場合、2,500万円を持ち戻して計算するため、相続税計算は1億2,500万円が対象となります。
本制度は贈与税を支払わなくてもよい代わりに、相続税が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、「相続時精算課税制度」は誰でも利用できる制度ではありません。
対象者は以下のように制限されています。
・贈与できる人(贈与者)は60歳以上の父母や祖父母
・贈与される人(受贈者)は18歳以上の子や孫
また、本制度は使用を開始する場合、相続時精算課税制度に関する所定の書類を税務署に対して届け出る必要があります。
法改正により、今後は年に110万円までの基礎控除が認められたため、「年間110万円」までの贈与なら贈与税もかからず、累計2,500万円までの特別控除にも含む必要がなくなりました。
以前よりも若干ではあるが、制度としてお得になったと言えるでしょう。
2024年の法改正も踏まえると、今後相続時精算課税制度はさらに利用者が増す可能性は高いでしょう。
高齢者から若年層へ財産を承継できる本制度に、関心を持っている方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、本制度は暦年贈与と比較すると利用が避けられてきた過去もあります。
その理由は主に以下の4つです。
まず1つ目は、「暦年贈与に戻れない」という点です。
年間110万円までの贈与なら非課税である暦年贈与は、広く活用されている贈与方法です。
暦年贈与は相続時精算課税制度とは異なり、贈与者・受贈者の双方に制限がありません。
自分の財産を誰に贈与しても適用される柔軟な贈与のしくみです。
ところが、一度相続時精算課税制度に切り替えてしまうと、便利な暦年贈与には戻れないのです。
長く暦年贈与を使っている方にとっては、相続時精算課税制度の魅力は低く感じるでしょう。
2つ目は、「必要書類が多い」点です。
相続時精算課税制度の利用にあたっては、選択届出書や受贈者の戸籍謄本などを提出する必要があり、こちらも暦年贈与と比較すると手続きがややこしいのです。
電子申告も可能だが、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、書類を整えて税務署に提出する必要があります。
次に3つ目は、「そもそもあまり知られていない」という問題です。
贈与は110万円までは贈与税がかからないという暦年贈与しか知らないという方は多く、相続時精算課税制度はもちろん、教育資金の一括贈与やおしどり贈与などはあまり知られていません。
贈与の方法には暦年贈与以外の選択肢もありますが、手続きの複雑さや対象者が限られているなどの理由から、見落とされる傾向があります。
最後に4つ目は、「贈与税の先送り、というイメージが強い」点です。
相続時精算課税制度は贈与時には税金を納めなくてもよいのですが、相続時にはその他の遺産と合わせて相続税計算をするため、結局相続税として税金を納めなければならない可能性もあります。
手続きがややこしく、税金も将来支払う必要があるなら…と本制度利用のメリットはない、と判断する人は多いでしょう。
これまで利用が避けられてきた相続時精算課税制度ですが、法改正後の今だからこそ知っておきたい「使うべき」4つの理由を紹介しています。
まず1つ目は、「値上がりしそうな財産の贈与はお得」になるという点です。
本制度の活用で高額の贈与をしても、2,500万円までは非課税となるほか、この金額を超えても贈与税の税率は一律20%しかかかりません。
暦年贈与は最大で55%の贈与税が発生するため、実は一気に行う高額贈与なら本制度の方がお得なのです。
相続時精算課税制度で贈与した財産は「贈与時の価額」で評価するため、将来的に値上がりする財産を贈与しておけば相続税対策にもつながるのです。
2つ目は、「高齢者の贈与に向いている」点です。
暦年贈与も法改正があり、これまで相続開始3年前までの贈与を相続財産に持ち戻しする必要がありましたが、今後7年へと段階的に延長されます。
高齢者にとっては病気などをきっかけに贈与を始めても、思うような相続税の節税効果が得られない可能性があります。
高額の財産を贈与するなら、少しずつ暦年贈与するよりも、思いきって相続時精算課税制度を選択することも検討の余地があります。
次に3つ目は、「110万円の基礎控除の誕生」です。
これまでこのしくみがなかったため、たとえ少額であっても相続時精算課税制度を利用するなら贈与税申告が必要でした。
しかしながら、110万円の基礎控除枠ができたことにより、この金額以下なら申告は不要です。
以前よりも制度が使いやすくなったのです。
また、毎年110万円までの贈与は、相続時の持ち戻しの対象外となる点も注目したいですね。
最後に4つ目は、「相続トラブルを防ぐ効果がある」点です。
相続人間で争う可能性がある財産を贈与であげたい人に渡してしまえば、遺産分割協議時に争いは起きにくくなります。
遺言書を使う方法も考えられますが、1つ目に触れたように値上がりしそうな財産は早期に渡すことで相続税の節税効果も得られます。
特に資産が多い方は、本制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
魅力が多い相続時精算課税制度ですが、暦年贈与に戻れない以外にも意外な落とし穴もあるのです。
まず、不動産の贈与時には税金への注意が必要です。
登録免許税と不動産取得税の負担がそれぞれ重くなる可能性があります。
相続時よりも贈与時の方が税率は高いため、事前に税理士に相談し計算結果を見てから判断することもおすすめです。
小規模宅地等の特例も使えなくなるため、不動産の贈与は慎重に進めてほしいですね。
また、本制度は孫へ贈与できる点が魅力ですが、相続人ではない孫(代襲相続除く)は相続税が2割加算となるのです。
今回は相続時精算課税制度について、2024年最新の情報を交えながら解説しています。
本制度は今後も利用率が伸びていくと思われますが、先述のとおり、意外な落とし穴があることも忘れずに利用してほしいですね。
相続時精算課税制度以外にも、相続税対策には遺言書や家族信託の活用なども考えられます。
いずれの方法でも、相続開始後のトラブルを未然に防ぐために、家族で資産形成のゆくえについて話し合いをしたうえで制度利用を決めましょう。
特に高額の贈与は、もらえなかった方に「なぜ自分はもらえなかったのか」という禍根を残してしまうおそれがあります。
明るい相続を目指すためにも、贈与の段階から丁寧な話し合いを重ねておきましょう。
先日、とある金融機関の方から、持ち戻し期間が3年から7年になった一方、相続時精算課税に非課税枠ができたわけですから、使わないと損じゃないですか?と聞かれましたが、メリットばかりではなく、デメリットもあることをお伝えしました。
安易に相続時精算課税を選択するのではなく、慎重に選択して欲しいですね。
生前贈与が税制改正でお得になり「相続時精算課税制度」を使うべき4つの理由について、あなたはどう思われましたか?
ハイデイ日高の創業者が創業50周年で従業員へ株4億円分贈与!
埼玉新聞社によると、埼玉県内を中心に中華料理店「日高屋」などを展開しているハイデイ日高(さいたま市大宮区、青野敬成社長)の創業者で、代表取締役会長の神田正氏は、自身の保有株式の一部約4億円分を従業員に贈与することを、先日発表しました。
2018年以来、2度目の実施となります。
贈与する株式数は約20万株(2023年4月5日現在、約4億2千万円相当)で、対象者は役員、正社員のほか、条件を満たしたパート・アルバイト従業員で、2023年6月の実施を予定しています。
今回の贈与は、株式公開から20年以上が経過し、2023年2月に創業50周年の節目を迎えた同社の発展に尽力し、共に働いてきた従業員への感謝の気持ちを込めています。
神田会長は「会社が成長して、利益を社員に還元する『分かち合う資本主義』を大切にしていきたいと思っている」とし、従業員への還元によって、安心して働ける環境を整備していくそうです。
たまに見かけますが、なかなかできないことだと思いますので、すごいですね。
こういう会社で働く方は幸せでしょうね。
ハイデイ日高の創業者が創業50周年で従業員へ株4億円分贈与したことについて、どう思われましたか?
生前贈与の相続税加算は「7年に拡大」軸に調整!
読売新聞によると、政府・与党は生前贈与を行う際の相続税の加算期間について、7年を軸に広げる方向で調整に入ったようです。
相続税がかかる加算期間をのばすことで、早めに若年世代への資産移転を促す狙いがあります。
生前贈与には、年間110万円までは贈与税がかからない「暦年課税」と、相続時に贈与税と相続税の差額を精算する「相続時精算課税」の2種類があります。
このうち暦年課税は、死亡前の3年間に相続人が受け取った資産は相続税の対象になります。
3年の加算期間を7年に拡大することにより、税負担を軽減しようと前倒しで生前贈与を行う動きが進むことが期待されます。
一方、相続時精算課税については、少額の贈与を申告不要とする方向で調整を進めており、額は今後詰めるようです。
現在は少額贈与でも税務署への申告が義務づけられています。
2022年12月15日に令和5年度税制改正大綱が公表されると言われていますが、個人的には、これが何年になるのかに最も注目しています。
長くなると、相続税対策も変わってくるでしょうから。
今年、お手伝いさせていただいた相続税の申告案件も、ちょうど半分、3年以内の贈与を足し戻す案件でした。
生前贈与の相続税加算は「7年に拡大」軸に調整していることについて、どう思われましたか?
政府の税制調査会が相続税・贈与税の専門家会合を設置!
日本経済新聞によると、政府の税制調査会(首相の諮問機関)は、先日の総会で、相続税と贈与税のあり方を議論する専門家会合を設置すると決めました。
贈与税は相続税の負担回避を防ぐために相続税よりも高い税率がかかる一方、多額の資産を持つ人が分割して贈与する場合は税率が低くなるため、格差の固定化につながらないような税制のあり方を議論します。
政府の税制調査会の中里実会長(東大名誉教授)は総会で「資産移転の時期の選択に中立的な税制に向け、どのように対応できるかが当面の課題となる」と述べました。
贈与税の課税方式には毎年の贈与額に累進税率を適用し、年間110万円まで非課税になる暦年課税制度と、60歳以上の贈与側1人につき2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度の2つがあります。
政府が富裕層向けに相続税の節税対策を強化するため「暦年課税を廃止するのではないか」との見方が一部にあります。
中里氏は総会後の記者会見で「そういった議論はせずに、理論的・実務的な観点から議論してもらう」と強調しました。
資産税に関わる僕らにとって、数年前からの贈与税の見直しの方向性の話しは、非常に気になるところです。
改正になると、過去の相続税対策が無意味なものになる可能性もありますし、今後の相続税対策が今までとまったく違ったものになる可能性があるからです。
個人的には、暦年贈与の廃止や縮小などが噂されていますが、どうせ改正するなら、失われた30年間と言われるように、給料がほとんど上がっていない状況を少しでも解消するために、ためこんで相続が発生するよりは、贈与をしてもらって、消費にあて、日本経済の活性化につながるような改正方向になればいいなぁと思っています。
政府の税制調査会が相続税・贈与税の専門家会合を設置したことについて、どう思われましたか?
被相続人からの毎年一定額の入金は相続財産に該当しないと認定!
TabisLandによると、被相続人が毎年一定額を入金していた未成年であった者の名義の普通預金口座に係る預金が相続財産に含まれるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、被相続人が作成した贈与証に基づく贈与を未成年であった者の母親が受諾し、入金していたものであるから、その普通預金口座に係る預金は当時未成年であった者に帰属する財産であり、相続財産には含まれないと認定して、原処分の一部を取り消しました。
この事件は、審査請求人が、相続税の修正申告において課税価格に加算した請求人及び兄名義の普通預金はいずれも相続開始日の3年より前に被相続人から贈与されたものであるから、相続税の課税対象ではないとして更正の請求をしたのが発端となったものです。
これに対して原処分庁が、兄名義の預金についてのみの請求を認める減額更正処分等を行ってきたことから、請求人が請求人名義の預金も請求人の母が親権者として受贈済みであるから原処分庁の認定には誤りがあるなどと主張、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案です。
現金預金が相続財産に含まれるか否か、贈与された時期はいつか、請求人名義の預金が相続財産に含まれるか否か(具体的には、請求人名義の預金は被相続人と請求人のいずれに帰属するものか)が争点になった事件ですが、原処分庁側は、請求人の亡父(被相続人)が毎年一定金額を当時未成年だった請求人に贈与する旨を記した贈与証を作成した上で、請求人の母を介して請求人名義の普通預金口座に11年間にわたって毎年入金していたことについて、請求人の母親が贈与証の具体的な内容を理解しておらず、被相続人の指示に従って普通預金口座に入金していたにすぎず、その入金が請求人へ贈与されたものとは認識していないのであるから、被相続人から請求人への贈与は成立しておらず、その預金は被相続人の相続財産に含まれる旨主張して、審査請求の棄却を求めました。
裁決は、贈与証の内容はその理解が特別困難なものとはいえない上、請求人の母親は贈与証を預かるとともに、被相続人の依頼により預金口座へ毎年入金し、預金口座の通帳等を口座開設当時から管理していたことからすれば、入金が開始した当時、請求人の唯一の親権者であった母親は請求人の法定代理人として贈与証による贈与の申込みを受諾し、その履行として普通預金口座へ毎年入金していたと認めるのが相当であると指摘しました。
また、普通預金口座には、利息を除き、毎年の入金以外に入金はないのでから、預金口座に係る預金は口座開設当初から請求人に帰属するものであって、相続財産には含まれないと判断し、原処分の一部を取り消しました。
いわゆる名義預金の話ですが、事実認定の話になりますから、なかなか難しいですね。
僕自身も、過去に税務調査で名義預金だと指摘され、反論をしたものの、詳細は述べませんが、確固たる証拠を提出することが物理的にできず、反論が認められなかったことがありますが、この事案は認められて良かったですね。
生前から相続税対策などで関わることができれば防げることは色々とあると思うのですが、相続が発生した後に相続税の申告を頼まれることが圧倒的に多いため、少しでも生前からお手伝いできればいいなぁと改めて感じた1件でした。
被相続人からの毎年一定額の入金は相続財産に該当しないと認定されたことについて、どう思われましたか?
妻名義の証券口座への入金はみなし贈与に該当しないと判断!
TabisLandによると、夫名義の預金口座から妻名義の証券口座に金員が入金されたことが、相続税法9条が定める対価を支払わないで利益を受けた場合つまりみなし贈与に該当するか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、妻名義の証券口座において夫の財産がそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるとして、対価を支払わないで利益を受けた場合には該当しないと判断、原処分を取り消しました。
この事件は、夫名義の預金口座から出金され、妻(審査請求人)名義の預金口座等に入金された金員に相当する金額について、原処分庁が相続税法9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当すると判断、妻(請求人)側に対して贈与税の決定処分等をしてきたのが発端です。
そこで妻側が、そうした金員の財産的な移転はなく、何らの利益も受けていないと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案です。
原処分庁側は、請求人の夫名義の預金口座からの金員が入金された請求人名義の証券口座について、①請求人自身の判断で取引を行っていたこと、②証券口座の投資信託の分配金が請求人名義の普通預金口座に入金されていたこと、さらに③その分配金等を請求人の所得として確定申告がされていたことなどを理由に挙げて、妻の証券口座への金員の入金は、相続税法9条が規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけです。
裁決はまず、夫婦間における財産の帰属については、①財産又は購入原資の出捐者、②財産の管理及び運用の状況、③財産の費消状況等、④財産の名義を有することとなった経緯等を総合考慮して判断するのが相当であると指摘しました。
その上で、①請求人は入金の前後を通じて夫の財産の管理を主体的に行っており、その管理に係る全部の財産について請求人に帰属していたものと認めることはできないから、証券口座において請求人自身の判断で取引を行った事実をもって利益を受けたと認めることはできないうえ、②分配金等の入金があっても、請求人が私的に費消した事実が認められないこの事案においては、これを管理・運用していたとの評価の範疇を超えるものとはいえず、③確定申告をしたことは、申告をすれば税金が還付されるとの銀行員の教示に従い深く考えずに行ったものとした請求人の主張が不自然とまではいえず、ことさら重要視すべきものとは認められないことなどの諸々の事情を考慮すれば、妻の証券口座への入金によっても、夫の財産は、証券口座においてそのまま管理されていたものと評価するのが相当であると認定しました。
その結果、妻名義の証券口座への入金は、請求人に贈与と同様の経済的利益の移転があったものと認めることはできず、相続税法9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合には該当しないと判断、原処分を全部取り消しました。
事実認定の話になるので、なかなか難しい案件だと思いますが、納税者側の主張が認められたことはいいことですね。
一般的に、税務調査において、名義預金とか名義有価証券とか名義保険というもので相続税を取ろうとしますが、それとは逆のパターンですから、もっと明確なものを示して欲しいなぁと思いますね。
妻名義の証券口座への入金はみなし贈与に該当しないと判断したことについて、どう思われましたか?
小室圭さんが振り込んだ解決金409万円に関し「夫婦間贈与」を専門家が解説!
NEWSポストセブンによると、4年にもわたりくすぶり続けた金銭問題に、とうとう終止符が打たれました。
秋篠宮家の長女・眞子さん(30)と結婚した小室圭さん(30)の母・佳代さんと元婚約者の金銭トラブルに関して、小室さん側から元婚約者に対し解決金409万3,000円が振り込まれました。
2021年4月に「28枚文書」で「解決金を払わない理由」を長文で綴っていた小室さんでしたが、アメリカへ渡る直前、電撃的に解決に動きました。
新婚生活のために渡米する2日前の11月12日、元婚約者が圭さんの母・佳代さんに貸したと主張する約400万円を額面通りに支払うことで双方が解決とする書面が取り交わされると、渡米後の11月15日、ついにそれが振り込まれました。
小室さんがこの400万円をどのように工面したのかは明らかになっていませんが、結婚した夫婦の一方がもう一方と金銭のやりとりをすることは普通に考えられ、何もおかしいことではありません。
しかし、日本の税制には贈与税というものがあり、金銭の贈与には一定の税金がかかるのです。
それがたとえ夫婦間であっても、1年当たり110万円を超える財産の贈与には贈与税がかかるのです。
円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏は、「夫婦間でお金を渡した、振り込んだといった金銭の授受があった場合、それが“あげた”なのか“貸した”なのかが問題になります」と話しています。
「“立て替える”という言葉がありますが、金銭の授受があっても、返済の意思があって、分割でもいいので返せば贈与にはなりません。また、生活費等を管理しやすいようにまとめるために夫から妻に振り込んだ、といった場合も問題は生じません」(橘氏)
贈与であれば、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日に申告をして納税しなくてはなりません。
しかしながら、通常夫婦間で貸借の契約書を交わすことはまれであり、将来的に返済すれば贈与にはならないため、金銭のやりとりだけで問題になるケースはほとんどありません。
夫婦間の贈与が問題になるのは、不動産を購入した際に支払った割合と名義が異なるケースや、どちらかが亡くなり相続税の申告が必要になるケースがほとんどです。
橘氏は今回の小室さんの件にも触れ、「制度上、仮に眞子さんの財産から払われていたとしても、分割払いでもいいので小室さんが妻に返済すれば問題ありませんし、個人間の金銭貸借のため利息をつけてもつけなくても構いません。肝心なのはそれが贈与なのか貸借なのか、お互いの認識です」と話しています。
お金に色はついていません。
今回の解決金の出所は夫婦にしか分からないのが現実です。
職業柄、相続関連のお仕事をしておりますが、『贈与はお金を口座に振り込んでおけばいいんでしょ?』とおっしゃられる方が結構います。
それに対して僕は、『例えば、お母さまからお子さまの口座にお金が振り込まれたとして、それが贈与なのか借入金なのか客観的に分かりますか?』と答えています。
客観的に分からないのは明らかでしょう。
そして、『それが問題となるのは、お母さまがお亡くなりになったあとの相続税の税務調査などでしょうから、既に当事者がいないわけですから。』と。
夫婦間であろうと、親子間であろうと、おじいちゃんおばあちゃんから孫であろうと、贈与するのであれば、贈与契約書・金銭消費貸借契約書をきちんと作りましょうということです。
小室圭さんが振り込んだ解決金409万円に関する「夫婦間贈与」の専門家の解説について、どう思われましたか?
「2億5千万を贈与」との詐欺メールで70代男性が8千円被害!
秋田魁新報によると、秋田県警鹿角署は、先日、秋田県鹿角市の70代男性が特殊詐欺に遭い、電子マネー利用権8千円分をだまし取られたと発表しました。
秋田県警鹿角署によると、先日、男性の携帯電話に「2億5千万円を贈与します」と記載されたメールが届き、贈与のため必要な名義変更などの費用として、電子マネーを購入するよう指示されました。
男性は2日間にわたり、鹿角市内のコンビニを複数回訪れ、要求どおり電子マネー計8千円分を3回に分けて購入しました。
そして、相手から指示されたサイトに電子マネーの利用に必要な番号を入力しました。
秋田県警鹿角署は、「多額の現金を贈与するとの名目で電子マネーをだまし取る特殊詐欺の手口。同様のメールが来たら警察に相談してほしい」と呼び掛けています。
いまだに、このような詐欺にひっかかる方がいらっしゃるんですね。
関係のない方が多額の贈与をしてくれるというおいしい話はないと思いますし、何かをもらうのに先にお金などを支払うというのはそもそも怪しいですよね。
電子マネーの購入という時点で、詐欺という気はしますが。
被害が8千円ですんで良かったと思いますが、こういった事件はなくなってほしいと思いますし、だます方も、その能力をまっとうな商売に使ってほしいですね。
「2億5千万を贈与」との詐欺メールで70代男性が8千円被害にあったことについて、どう思われましたか?
生前贈与は「愚の骨頂」?
しかしながら、長男に渡せば次男も「自分にも贈与してくれ」と言い出してくるなど、かえって揉めごとを招く原因になることがあります。
自分で稼いだおカネは自分で遣えばいいでしょう。
それでも余ったおカネがある場合、「遺贈寄付」という手があるのです。
遺贈寄付とは、あらかじめ遺産の寄付先を決めておき、自分が死んだら引き渡してもらうことです。
胃がんで2年前から闘病生活を送っている米沢康太さん(76歳・仮名)も、遺贈寄付を計画しているそうです。
「金遣いの荒い息子におカネをくれてやるくらいならと思い、治療でお世話になっている国立がん研究センターへの遺贈寄付を思い立ちました。
がん研究センターには、立派な銘板に寄付者の名前がズラリと並べられている。私のカネが世のため人のためになり、名前まで残せるなら、こんなにうれしいことはない」
米沢さんのように、自分の関心や趣味に従い遺贈寄付を選択する人は、年々増えているそうです。
たとえば、母校の大学を指定して寄付を行うと、自分の名前を冠した奨学金を設立できるケースもあり、後輩の学業を助けることができます。
実際の遺贈寄付の手順は極めてシンプルです。
「遺言書に寄付先の団体と金額を明記し、司法書士などの遺言執行者を指定する。寄付先の団体に事前に伝えておくと、先方もありがたい。
寄付をできるのは現金のみというところも多いので、不動産を寄付したい場合は要確認です」(司法書士の村山澄江氏)。
感謝されて生きた証も残せるため、一石二鳥です。
相続で揉めることは結構ありますが、仲が良かった兄弟姉妹などが相続をきっかけに仲が悪くなるのは残念でありません。
そうなることを防ぐためにも、相続人ではなく、財産を持っている方ができるだけ早く、相続のことを考えましょう。
その中の選択肢の一つが、生前贈与とか遺贈寄付だと思います。
ちなみに、税理士のところには、毎年、日赤から『遺贈・財産寄付ご案内パンフレット』というものが送られてきます(笑)。
生前贈与は「愚の骨頂」?について、どう思われましたか?
サラリーマン家庭でも増えてきた「生前贈与」封じのため改正に動く財務省の言い分!
文春オンラインによると、サラリーマン家庭の間でも増えている相続税の節税策が、近々封じられる可能性があるそうです。
相続税は、一定額以上の財産を持つ富裕層に課せられてきたものですが、2015年の課税ライン引き下げにより課税対象者が増えたことで世の関心が高まり、サラリーマン家庭または定年退職者でも生前の節税策に着手する人が増えています。
その代表は、親の課税対象財産を減らして将来の相続税を軽減するために、親が子や孫に財産の一部を生前贈与することです。
国は、財産の移転に関しては人が亡くなった時の相続税で課税することを基本としています。
課税されることが分かれば、人は生前に財産を贈与して課税を回避しようとするため、相続税を補完するものとして贈与税を作り、1年毎に、贈与額に応じて累進で10%~55%の贈与税を課しています(いわゆる暦年贈与)。
この贈与税の税率は相続税の税率より高く設定され、相続を待たずに生前贈与すれば損する仕組みとなり、生前贈与が抑制されてきました。
ただし、贈与税には特例が設けられ、1人につき誰からもらったかは問わず年間110万円までの贈与は非課税になっています。
これを利用して、親が子や孫にそれぞれ年間110万円ずつ生前贈与するという節税策に着手する人が増えているのです。
1人当たり年間110万円の贈与でも効果は小さくないのです。
例えば、父親が8,000万円の財産を持ち、相続人が子供2人の場合、計470万円の相続税がかかります。
これに対し、父親が子供2人と孫2人の計4人にそれぞれ年間110万円(合計440万円)の非課税贈与を2年間続ければ、相続税は概算で計338万円まで下がり132万円の節税になるのです。
もちろん、期間が長くなれば、節税効果は大きくなっていきます。
生前贈与については、「贈与すれば子供が浪費するだけ」「財産を貰ってしまえば子供は親の面倒を見なくなる」といった指摘もあるのも事実です。
親の財産や家族の状況を見極める必要はありますが、非課税贈与を続ければ節税額は増え、課税ラインを下回って相続税をゼロにすることもできます。
国の制度は、上手に利用する人が得をして、そうでない人が損をしますが、生前贈与はその1つと言えるでしょう。
この生前贈与を最も利用しているのは富裕層でしょう。
年間110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、贈与税を払ってでも生前贈与したほうが相続税の軽減が図れるケースもあります。
ちなみに、2019年の1年間に贈与された額は全体で2兆430億円あまりとなり、1,000万円を超える贈与を受けた人は約1万5,000人に上ります(申告分。相続時精算課税分を含む。)。
当然、年間110万円以下であれば申告は必要ないため、実際にはかなりの額になるでしょう。
問題は、この生前贈与が税制改正によって封じられる可能性があることです。
税制改正の“建前”上の理由は、「若い世代への資産移転の促進」です。
日本では高齢者への資産偏重が進んでいます。
財務省が税制改正に向けて2018年10月に示した資料によれば、個人の金融資産約1,700兆円のうち、60歳以上の人がその約6割(1,000兆円)を保有するに至り、この20年間で倍増しています。
また、高齢化の進行により、2016年には、死亡時の年齢が80歳を超えている親が7割に達しました。
80歳を超えた親の資産を50歳以上の子供が相続するといった、高齢者が高齢者に財産を相続するケースが増えています。
財務省は、この現象を「老老相続」という言葉で表現し、「相続による若年世代への資産移転が進みにくい状況となっている」と問題視しています。
子育てや住宅の購入など支出が多い30代~50代を過ぎた後に財産を相続しても、有効に活用されないからです。
2020年12月の与党の税制改正大綱でも、経済を活性化するために「資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要」として検討課題に挙げられました。
ここで出て来たのが「相続税と贈与税の一体化」です。
生前贈与には贈与税を課さず、相続時に、生前贈与された分も加えて相続税を課し、財産の贈与時期を選択できるようにする方向が示されています。
その具体化は進んでいませんが、先行されると見られるのが「3年ルール」の延長だそうです。
親が亡くなり相続が発生すると、亡くなってから過去3年間の贈与は相続財産に加算して相続税の課税対象になると定められています(相続税法第19条)。
つまり、贈与税を払って贈与していても、年110万円の非課税贈与を続けていても、課税対象なってしまう(贈与がなかったものとされる。)のです。
3年間の生前贈与を認めないのは、親の死を前にした駆け込み贈与により、相続税の節税を防ぐためとされています。
生前贈与は「早めに着手するべき」と言われるが、その理由の1つはここにあります。
財務省の資料では諸外国の例を挙げ、英国は過去7年分、ドイツは過去10年分、フランスは過去15年分、アメリカは過去全ての生前贈与を相続税の課税対象にしていると説明されており、日本の3年ルールの延長が示唆されている(ただし、世界には相続税のない国もあり、アメリカは基礎控除額の10億円を超えて課税されるのはごく一部であるなど、相続税制度そのものが各国で異なり、このルールだけを当てはめようとすることに批判があります。)。
前述の税制改正大綱では、「現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある」としており、3年ルールの延長は富裕層の節税封じも目的にあると見られます。
しかしながら、同時に、現行の3年ルールで110万円の非課税贈与も対象となっていることから、期間が延長されれば同様にすでに贈与した分についてもそのまま対象になる可能性があります。
10年、15年、またはそれ以上に延びれば、サラリーマン家庭でもできるささやかな節税策が封じられてしまうのです。
相続税制では抜け道があれば広まり、広まれば国税庁が封じるイタチごっこが続いてきました。
予想以上に110万円の非課税贈与の利用者が増えており、それを封じるための改正にも見えます。
「相続税と贈与税の一体化」は、僕を含め資産税系の税理士にとっては、非常に気になるところです。
税金単独ではなく、社会保障などとの絡みもありますので、個人的には、都合がいい時だけ諸外国と比べることはあまり意味がないと考えています。
税理士として普段から暦年贈与のお話しや提案などをしていますが、改正のリスクをきちんと伝えておかないといけないのはもちろんですが、改正がどうなるか分からないので、提案もしにくい状況です。
2021年12月に出る税制改正大綱で改正が行われるとは思いますが、我々税理士としては、スタート時期もとても重要です。
例えば、4月から改正になるのであれば、12月中旬から3月までに実行しないといけませんので。
どのような改正になるかウォッチし、早めに適切な対応ができればいいなぁと考えています。
サラリーマン家庭でも増えてきた「生前贈与」封じのため改正に動く財務省の言い分について、どう思われましたか?
すぐに贈与税の申告ができない!
2021/4/15に自分の確定申告を終え、今シーズンの確定申告業務が終わりました。
昨シーズンは、自分を除き、当初の期限である3/15に終えたのですが、今シーズンは、3/16以降に申告を終えた方がそれなりにいて、4/14にも2名電子申告をしました。
備忘録を兼ねて、今週は、今回の確定申告で感じた留意点をまとめたいと思います。
<所得税>
①事業的規模でなくても65万円控除ができる!
②役所を信じてはいけない!
<消費税>
③雑所得でも所得税の還付申告ができる!
④新型コロナウイルス感染症の影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!
<贈与税>
⑤すぐに贈与税の申告ができない!
すでに、『事業的規模でなくても65万円控除ができる!』、『役所を信じてはいけない!』、『雑所得でも所得税の還付申告ができる!』、『新型コロナウイルス影響があれば簡易課税・原則課税を変更できる!』については書きましたので、最終回の本日は、『すぐに贈与税の申告ができない!』です。
贈与税には、①暦年課税と②相続時精算課税とがあります。
<1.暦年課税>
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
<2.相続時精算課税>
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。
それにより贈与税額が分かります。
<贈与税の速算表>
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
|
200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
|
|
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
|
控除額 |
- |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。
|
基礎控除後の課税価格 |
200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
|
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
|
控除額 |
- |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
基本的には、贈与税の申告書は1ページのみです。
しかしながら、「特例税率」の適用を受ける場合で、以下の①または②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出する必要があります。
ただし、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入することにより、当該書類を重ねて提出する必要はありません。
①「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき
②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価格((注)参照)が300万円を超えるとき
(注)「一般贈与財産」について配偶者控除の特例の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた後の課税価格となります。
つまり、祖父母や両親などから贈与された金額が410万円を超えると、もらった方の戸籍の謄本の入手が必要になります。
市役所の出先機関であるコミュニティセンター内の出張所でも可能ですが、すぐにというわけにはいかないかもしれません。
よって、贈与税の申告直前になって慌てて入手するのではなく、余裕を持って入手しておくことをお勧めします。
ちなみに、電子申告の場合、戸籍の謄本はイメージ添付できますので、原本を提出する必要はありません。
あと、贈与税の申告以前に、当然、『贈与』という行為が必要ですが、そもそも『贈与』はあげる方のあげるという意思ともらう方のもらうという意思がないと成立しません。
もちろん、口頭でも成立はしますが、後日、税務調査が入った時などに、『贈与』であるという証明が困難で、対応に苦慮する可能性があります。
特に、相続税の税務調査の時に『贈与』が論点となることが多いため、『贈与』してから数年後、数十年後に『贈与』があったことを証明する必要が生じる可能性があるため、個人的には、贈与契約書を作成し、それなりの金額の場合は、公正役場で『確定日付』を取ることをお勧めしています。
なお、『確定日付』は内容の正確性などを証明するものではありませんが、その日に存在していたことを証明する日付の入ったスタンプを押してもらうものです。
ところが、公証役場は、平日の昼間しか開いておらず、それほどたくさんあるわけではありません(我が香川県は高松市と丸亀市の2か所のみ)ので、急ぎで作成が必要な場合、土日祝や早朝や夜間は、『確定日付』を押してもらうことができません。
そこで、『確定日付』ほどの効力はないと思いますが、その日に、その贈与契約書が存在していたことを示すためには、郵便局で、贈与契約書に切手を貼って、『記念押印』をしてくださいと言うと、切手のところに郵便局の日付の入ったスタンプを押してくれますので、それも良いかと思います。
ちなみに、郵便を出した際に通常切手に押されているのは『引受消印』と言うそうです。
また、『記念押印』の場合、最低63円の切手を貼る必要があります(郵便局の担当者が『記念押印』のことをよく知らない場合、それ未満でも押印してくれるケースはありますが。)。
よって、公証役場が開いていない場合、『確定日付』の手数料700円がもったいない場合などは、『記念押印』という手もあります。
すぐに贈与税の申告ができないことがあることについて、どう思われましたか?
小室佳代さんは報道を受け時効ギリギリで「贈与税」支払っていた!
女性自身によると、秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が延期となっている小室圭さんが先日、母・佳代さんと元婚約者X氏との「金銭トラブル」について説明する文書を発表した。
その中で、小室さんはこう記しています。
《平成24年(2012年)9月13日午後11時15分、母は元婚約者の方から、婚約を解消したいという一方的な申し入れを突然受けました。(中略)このとき母が、婚約期間中に受けた支援について清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者から『返してもらうつもりはなかった』というお返事が返ってきました》
実は小室さんが金銭トラブルについての説明文書を発表するのは2度目のことです。
2019年1月22日に公表された文書でも、X氏の「返してもらうつもりはなかった」という発言から、金銭的な問題はすべて解決済みと認識してきたと説明していました。
しかしながら、前回の文書発表直後の2019年2月、WEB女性自身では「小室圭さんの母・佳代さんに脱税疑惑…税務調査の可能性も」との記事を配信しています。
X氏から佳代さんに渡されたという409万円が、小室さんの説明通り返済の必要がない金銭なのであれば、贈与税を納めなければいけないのではないかという疑惑です。
贈与税の時効は贈与があった翌年3月から数えて7年です。
佳代さんがX氏から金銭を受け取ったのは2012年1月の200万円が最後だったので、その時点で、時効は2020年3月に迫っていたのです。
女性自身は、当時、小室圭さんの代理人・上芝弁護士にこの疑惑について電話で質問したそうです。
しかしながら、上芝氏は質問の核心には触れず、409万円の金銭が贈与だったのか貸与だったのかについても明言を避けました。
佳代さんが贈与税を納付したかどうかについて、この時点で真相を掴むことはできなかったのです。
しかしながら、今回の小室さんの文書には、注釈の部分にこんな一節がありました。
《なお、贈与税を負担しているのかという報道がありますが、母は贈与税を納付しています。それまでは贈与税を納付する必要があると思っていなかったのですが、報道の後に知人から贈与税は納付しているのかと聞かれたことがきっかけで、念のためにということで納付しました》
小室さんは、女性自身の指摘に応えるように、佳代さんの“脱税疑惑”もしっかり晴らしていたようです。
贈与は、あげる方のあげるという意思と、もらう方のもらうという意思で成り立ちます。
そして、誰にもらったかは関係なく、1月1日から12月31日の間にもらった額が110万円を超えると、原則として、贈与税が課税されます(110万円までは贈与税がかからないという、いわゆる暦年課税)。
申告漏れのないようにしたいですね。
小室佳代さんは報道を受け時効ギリギリで「贈与税」支払っていたことについて、どう思われましたか?
身元保証の愛知県のNPO法人が死後全額贈与契約で敗訴!
日本経済新聞によると、身寄りのない高齢者の身元保証を請け負う愛知県安城市のNPO法人が、死亡した高齢者との贈与契約に基づき、預金全額の支払いを金融機関に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁岡崎支部は、先日、「契約は公序良俗に反し無効」として請求を棄却しました。
判決によると、このNPO法人は2017年1月、安城市社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の80代女性と身元保証契約を締結し、翌月には、死亡後に不動産を除く全財産を贈与するとの契約も結びました。
女性は2018年7月に死亡し、このNPO法人が安城市の碧海信用金庫に預金約620万円の支払いを求めていました。
近田正晴裁判官は判決理由で「契約は不必要で内容も不明確。死後事務処理の費用は50万円ほどなのに、預金全額を受け取るというのは対価性を欠き、暴利と言わざるを得ない」と指摘しました。
さらに、ホームの入所者の半数以上が同会と身元保証契約を結んでいることや、同会代表者の夫が、安城市社会福祉協議会を指導する立場の安城市職員だったことから「契約の背景には市や社協、会との間の癒着構造が認められる」とも批判しました。
このNPO法人の代表は「多くの人を支援してきたのに、癒着は事実無根で、名誉を傷つけられた」とし、控訴する方針だそうです。
安城市高齢福祉課の担当者は「癒着はなく、裁判所の判断に戸惑っている」と話しているようです。
最近、身元保証業務を事業として取り組んでいる会計事務所があるようで、少し気にはなっていたのですが、こういうことを言われる可能性があるんですね。
認知症の問題もあり、贈与契約が有効かどうかということも難しいと思いますが、法を整備し、きちんとした団体等を作ってやっていかないと、悪質な業者等が出てくるような気はします。
家族信託もそうですが、専門家が契約書をきちんと作ることが重要ですね。
身元保証の愛知県のNPO法人が死後全額贈与契約で敗訴したことについて、どう思われましたか?
千葉銀行と千葉大学医学部付属病院が円滑な「遺贈」を後押し!
千葉銀行と千葉大学医学部付属病院は、相続人以外に財産を残す「遺贈」に関する協定を結んだそうです
病院に遺贈を申し出た希望者に対し、相談先として千葉銀行を紹介します。
千葉銀行は個別相談に応じたり、関連サービスを紹介したりして円滑な遺贈を後押しします。
遺贈は、遺言に基づき、相続の発生後に財産を法人やNPOなどに寄付するしくみです。
生前に意思を遺言書に残すなどの事前手続きが必要となります。
高齢化の進展に伴い、関連サービスのニーズが高まっています。
千葉銀行は病院から紹介された遺贈希望者に対し、1人につき1回無料で個別相談に応じるほか、遺言信託などのサービスを紹介します。
また、病院が高齢者向けセミナーなどを開く際、千葉銀行の行員を講師として派遣します。
千葉大付属病院が民間企業と遺贈に関する協定を結ぶのは初めてだそうです。
千葉銀行はこれまでに千葉市や松戸市といった千葉県内自治体のほか、日本赤十字社千葉県支部とも遺贈に関する協定を交わしています。
協定を結んだからといってどこまで案件があるのかは分かりませんが、個人的には、病院側がどうやって遺贈の話を持ち掛けるのかに興味があります。
あとは、金融機関は顧客を紹介すると紹介料を求めたりしますが、紹介してもらう場合はどうしているのかも気にはなりますね。
千葉銀行と千葉大学医学部付属病院が円滑な「遺贈」を後押しすることについて、どう思われましたか?
みのもんたさんが“後妻業の女性”に手切れ金1億5,000万円!
日刊ゲンダイDIGITALによると、みのもんたさん(76)が40歳年下の恋人に東京都港区にある1億5,000万円のマンションを贈与したと発売中の「週刊文春」が報じて話題だそうです。
相手は元銀座の高級クラブのホステス(35)で、7年前からの交際だそうです。
きっかけは彼女が勤めるクラブにみのさんが来店し、数日後に彼女が「お昼ご飯にお弁当を作ったので、よければ食べていただけませんか」と連絡し、「胃袋を掴まれた」のだそうです。
彼女は介護の学校の学費稼ぎのためにホステスに。糖尿病を患うみのさんの体調を気遣った弁当に、介護のプロならではの行き届いた気遣い、しかも27、28歳の美人とあらば、妻に先立たれた独り身の70男がコロリといくのは至極当然でしょう。
そんな“弁当交際”から4年後、彼女はホステスを辞め、介護士のパート仕事と、みのさんの面倒を見る生活にシフトし、みのさんはマンションに彼女を住まわせ、通っていたそうです。
みのさんは2019年末に持病の糖尿病に加え、パーキンソン病を発症し、これを機に、2020年3月に「秘密のケンミンSHOW」(読売テレビ系)を降板しました。
2020年12月には自身が経営するニッコクも社長を退く予定で、資産50億円を持つといわれるみのさんは終活状態です。
そんな中、先日、彼女に住まわせていた1億5,000万円のマンションの登記が、みのさんの会社であるニッコクから、みのさん個人、さらに、彼女に贈与移転しています。
同誌によると、彼女が再婚を望むも、子供たちに反対され“手切れ金”としてマンションを贈与したそうです。
家族問題評論家の池内ひろ美氏がこう言っています。
「一般的に女性が多額の資産を受け取ったとき、男性から離れていく可能性は高い。35歳の女性なら、後妻に入って“将来受け取ることができる資産”に関心は薄いでしょう。それより、結婚、出産、今まで積み上げたキャリアを生かした事業など、もうひと頑張りしたい時。むしろ2人の関係が公になったことで、次のステップに進むべく、結論を出したいと思っているのでは」
みのさんの会社に問い合わせると「彼女は友達。マンションの件は『ご想像におまかせします』とのことです」(担当者)とのことで、現在は鎌倉の家から出ず、隠遁生活しているそうです。
手切れに1億5,000万円という、夜の帝王に武勇伝がまたひとつ刻まれました。
個人的には、事実であるならば、手切れ金で1億5,000万円はすごいなぁと感じる一方、職業柄、贈与税はどうするのだろうか?(贈与税の申告・納税の期限は2021年3月15日までですので、まだです。)、贈与税も考慮のうえ、現預金も贈与したのだろうか?と下世話なことを考えてします(笑)。
また、マンションは元々、法人名義だったようですが、税務上、どう扱っていたのだろうか?と気になります。
みのもんたさんが“後妻業の女性”に手切れ金1億5,000万円と報じられていることについて、どう思われましたか?
甘利氏が「資産移転公平に」と相続税と贈与税の一体化に意欲!
自民党税制調査会は、先日、幹部会合を党本部で開きました。
甘利明税調会長は終了後、記者団に「相続税と贈与税に関し、海外ではいつ資産を移転しても公平で公正な制度がある」と述べ、二つの税の一体化に向けた見直しに意欲を示ましした。
日本では相続税と贈与税を原則として別々に適用しており、贈与税は「暦年課税」が中心で、生前贈与と死後の相続では税負担額が大きく変わります。
一方、欧米主要国では二つの税を統合して累積額に一体的に課税しており、資産移転の時期によって税負担が左右されにくい利点があります。
甘利氏は「国際標準に極力沿う形にしていきたい」と表明しました。
先日の与党税調総会から作業が本格化した令和3年度税制改正で議論する方針です。
ただし、相続税と贈与税については、政府税制調査会(首相の諮問機関)でも集中的に議論する専門家会合を年明けに設置するようです。
政府税制調査会の議論を待つべきだとの声もあり、結論を出せるかどうかは不透明のようです。
そもそも、日本でも、贈与税法というものは存在せず、相続税法の中に規定されており、昔から『贈与税は相続税の補完税』と言われています。
違いがあるからこそ、僕ら税理士にとっては相続税対策の提案などができたわけなので、どう改正されるかをきちんとウォッチしたいです。
令和3年度の税制改正大綱は、2020年12月10日に出るようですね。
場合によっては、相続税対策というものがガラッと変わるかもしれませんし、過去に相続税対策としてやったものが効果がなくなったり、減少したりするかもしれません。
甘利氏が「資産移転公平に」と相続税と贈与税の一体化に意欲を示したことについて、どう思われましたか?
樹木希林さんも実践した「孫への贈与」が相続対策として注目を集める!
女性セブンによると、新型コロナウイルスの影響で、相続対策について考え始める高齢者が増えているそうです。
「志村けんさんや岡江久美子さんが感染し急逝されたことで、自分にも“もしものことがあったら”と考える人が増え、相談に来るケースも増えています」と話すのは相続対策を行う夢相続代表の曽根恵子さんです。
一般的に相続対策とは相続税の節税を指すことが多いようです。
「うちは相続税がかかるほどの財産はない」と思っている人も少なくないでしょうが、2015年の民法改正で相続税の基礎控除額が大幅に変更され、相続税を支払う人は、2019年には全国で約12人に1人、東京都では約6人に1人まで、拡大しているのです。
「東京だけでなく、横浜や名古屋、大阪、京都、神戸、さらには福岡などの大都市圏に住んでいる人は油断禁物です。不動産や一定の金融資産を抱えていれば、相続税が発生する可能性があります。早めに対策をしておくことをおすすめします」(曽根さん・以下同)
相続といえば、被相続人が亡くなってから発生するものですが、それでは遅いのです。
亡くなる前に相続対策を取るか取らないかで、支払う税額に大きな差がつくからです。
なかでも注目したいのが、「孫への贈与」です。
実は2年前に亡くなった樹木希林さん(享年75)も孫への“贈与”を実践していた1人なのです。
樹木さんは合計10億円以上ともいわれる不動産を所有していたようですが、生前、「私が死んでも、夫に遺産は残さない」と宣言していました。
残された不動産はこの宣言どおり、娘の也哉子さん(44才)や娘婿の本木雅弘(54才)の名義に書き換えられましたが、所有していた不動産の1つは、樹木さんが存命のうちに孫の伽羅(21才)の所有になっていたようです。
「日本人全体の平均寿命が伸びたことで、遺産を相続する人が65才以上の高齢者というケースが増えています。これだと相続税を払って相続したものの、10年後にその人も亡くなり、再びその子が相続する際に相続税を払うという問題も現実的に起こっています。そこで一世代抜かして、孫に生前贈与する“相続対策”が注目されているのです。また、消費活動の盛んな孫世代に遺産が引き継がれるよう、孫への贈与が“お得”になる制度を国が用意しているんです」
配偶者と子供は民法で定められた相続人(法定相続人)となりますが、孫は含まれません。
そのため、さまざまな“抜け道”があります。
「孫相続」の賢いやり方を具体的に見ていきましょう。
生きている間に子供や孫に財産を渡すと、通常は贈与税が発生します。
しかしながら、年間110万円以内(基礎控除)なら非課税となります。
この仕組みを活用するのが「暦年贈与」で、親子より祖父母と孫で行うと、メリットが大きくなります。
暦年贈与は親子間でも可能ですが、子は法定相続人にあたるため、相続時に過去3年以内に行われた贈与はなかったものとされ、相続税がかかります。
ところが、(代襲相続人を除く)孫は法定相続人にあたらないため、過去にさかのぼって課税対象とならないのです。
「孫が10人いてもそれぞれ110万円まで非課税で渡せます。贈与したお金の使用用途に制限はありません。何年でも繰り返し暦年贈与を行うことができます」
ただし、毎年、定期的に同額を贈与するのはNGです。
「『連年贈与(定期贈与)』とみなされ、基礎控除が初年分しか適用されなくなる可能性があります。贈与する月を不定期にし、金額も1年目は100万円、2年目は90万円にするなど計画的な贈与にしない工夫が必要です。
ほかにも注意点があります。贈与を受ける孫が自分名義の口座を持ち、自分で管理することです。孫が未成年で自分で管理できない場合は、贈与する側の祖父母ではなく親が管理しましょう」
個人的には、早くから長期に渡って行う暦年贈与は非常的に簡単で効果的だと思っています。
しかしながら、この記事に疑問もあります。
『ただし、毎年、定期的に同額を贈与するのはNGです。』というのは、違うのではないかと思います。
『連年贈与』というのは、例えば、1,000万円を10年間で贈与する(1年当たりは100万円)という贈与契約がある場合に生じるものなので、そのような契約書を作る方はほとんどいないと思われるからです。
毎年、贈与契約書を作成し、実際にあげる方ともらう方の贈与の意思があれば、同じ日に同じ金額を贈与しても連年贈与と認定されることはないと考えています。
樹木希林さんも実践した「孫への贈与」が相続対策として注目を集めていることについて、どう思われましたか?
日本郵便のかんぽ不適正販売の「社員大量処分」の杜撰すぎる実態!
東洋経済によると、9月10日、全国の郵便局にある“指示”が出たようです。
タイトルは、「金融商品の販売時における税制の説明等の対応」です。
指示を出したのは、日本郵便本社の保険販売に関連する3人の部長です。
添付資料の「不適正なケースの具体例」を見て、かんぽ生命保険の契約を媒介してきた日本郵便の社員は思わずのけぞったそうです。
そこに書いてある具体例の多くが、かんぽや日本郵便の本社・支社が最近まで正しいとしてきた話法そのものだったからです。
●「相続税が下げられる節税プランをすすめます」は相続税対策ニーズを喚起している
●「相続税を減らせる」は税制の専門的な内容を断定している
●「相続税対策に保険を利用している人が多い」はニーズがない人に提案している
●「無対策で相続税が多くかかった人がいる」は第三者話法を使ってニーズ喚起している
として、不適正だとされました。
2018年4月付の研修用資料で、「生前贈与を含む生命保険を活用した相続対策提案」というものがあるようです。
冒頭の指示にある「不適正なケースの具体例」に照らせば、2年半前の多くの話法が不適正だったということになります。
「高齢のお客様にアプローチするときに、相続対策としてABA契約をテキストに掲載していた。契約者(子ども・A)、孫(被保険者・B)、契約者(受取人である子ども・A)の関係になる。相続税を大幅に下げる効果はなく、相続対策として有効ではない」。
これは2020年1月23日、北海道支社での社員との対話集会「第3回フロントライン・セッション」での日本郵便の長谷川篤執行役員の発言です。
本社の改革推進部は、「当日、孫と説明しましたが、テキスト上の記載は配偶者(相続人)でした」と当日の議事録「やり取り模様」に注意書きをしています。
しかしながら、東洋経済が入手した「テキスト」、すなわち社外秘の研修資料「かんぽで早めの相続準備」には、「孫」と明記されているようです。
同資料はかんぽが作成し、毎年最新版に更新してきたものです。
資料をめくると「暦年贈与を使って財産承継することも可能です!」と書いたページがあります。
「暦年贈与」とは毎年一定額を生前に贈与することです。
きちんと手続きを踏めば、年間110万円までは基礎控除となります。
そのページには、相続人である子どもが契約者(A)、孫が被契約者(B)、満期保険金の受取人は子ども(A)とする例が書いてあります。
保険料を実際に払うのは子どもの親であり、孫の祖父母に当たる高齢者です。
この事例は2018年版にも2019年版にも書いてあるようです。
保険料が年110万円を超えると生前贈与と見なされない。
単なる贈与と見なされ、節税メリットはない。
年110万円を超えなくても、贈与契約書を親子で取り交わしておかないと、生前贈与にはならない。
日本郵便は東洋経済の質問状に対して、「過去の研修資料にお客さま本位とは言えない表現が含まれていたことは事実。今後は真のお客さま本位の営業スタイルを募集人全体に浸透させていきたい」「管理者を含む関係者にも厳正に処分を実施しているが今後、不適正募集に直接的に影響した事実が判明した場合は、引き続き厳正に対処する」と回答したようです。
この記事では、赤字のことが書いてありますが、生前贈与というのは法律用語ではなく、俗語であり、遺贈とか死因贈与と区別するために使われることばだと思いますので、110万円を境に生前贈与か贈与かが変わるものではありませんので、記事を書いた方も分からずに書いていますね。
別に110万円を超えても、110万円を超える部分に対して贈与税がかかるだけであり、110万円部分には課税されませんので、この部分に関しては節税効果は当然ありますよね。
まぁ、相続とか贈与のことがよく分からず販売していた方もおられると思いますので、かんぽだから安心と思うのではなく、信頼できる方を通じて保険に入ってほしいと思います。
日本郵便のかんぽ不適正販売の「社員大量処分」の杜撰すぎる実態について、どう思われましたか?
祖父母から孫への贈与が非課税になる4つの制度!
週刊ポストによると、3世代にまたがる家族で、資産を“有効活用”するために重要となるのが「贈与」です。
高齢の祖父母が預貯金などの資産を抱えて亡くなると、その総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超えた分が、相続税の課税対象となるからです。
2015年に相続税の課税強化が実施されて以降、都内に持ち家がある場合などは対象になることが珍しくないため、あらかじめ子や孫へ贈与しておくことが資産の有効活用(節税)になるでしょう。
とりわけ「祖父母から孫」への贈与では“得する制度”が複数あり、主なものをまとめています。
まずは、ご存知の方が多い、年間110万円までの非課税枠がある暦年贈与です。
山本宏税理士事務所の山本宏税理士によると、「祖父母と孫の関係に限らず使える制度ですが、親子間の場合、贈与から3年以内に親が亡くなると相続財産に戻されて課税対象となってしまいます。これが孫の場合、もともと法定相続人ではないため、基礎控除以内の贈与は非課税のままで済むのです。」
さらに、結婚・子育て、教育資金、住宅取得資金などの用途に限定した一括贈与があります。
いずれも“期間限定”の制度です。
直系尊属からの贈与が要件なので、親子間でも使えますが、年齢差を踏まえると祖父母から孫への贈与が、相続財産の圧縮に使いやすくなっています。
「こちらは非課税枠の金額は大きいが、使い方に注意が必要です。とくに結婚・子育て資金の一括贈与は、祖父母が亡くなった時点で専用口座の資金が使い切れていないと、残りは相続財産に戻さないといけないので、節税メリットは小さい。
一方、教育資金は祖父母が亡くなっても、贈与を受けた孫が30歳になるまでに専用口座の資金を教育目的の使途で使い切れば課税対象にならないので、使い勝手が比較的いいでしょう。また、住宅取得資金は自宅購入時に贈与するので、“使い切れない”という心配はない。タイミングさえ合えば有効に活用しやすい」(山本宏税理士)。
ただし、メリットが大きいぶん、かえって“争続”のタネにもなり得るので注意しなくてはなりません。
「たとえば長男に子供(孫)が3人、次男には1人だった場合、すべての孫に均等に贈与すると、長男の世帯と次男の世帯の間では受け取った額に大きな差が生じ、亡くなった後の遺産分割で揉めごとが生じるリスクがある。あらかじめ贈与、相続でどのような配分をするか、家族で話し合って合意しておくのがよいでしょう」(山本宏税理士)
教育資金の一括贈与は、一時爆発的にヒットしましたが、数年前に改正され、少し使い勝手が悪くなりました。
領収書を提出したり、色々と手間もかかりますので。
ただし、すぐに財産を減らしたいときは有効な方法だとは思います。
税金は知らないと損することが多い(知らなくて損をしていても税務署は教えてくれない)ので、情報収集も必要だと思いますね。
祖父母から孫への贈与が非課税になる4つの制度について、どう思われましたか?
コロナ対策の生前贈与はかえって危険?
ガシェット通信によると、コロナウイルスの影響で、いつ誰が被害を受けてもおかしくない状況になってきています。
そのせいで今もし自分が死亡したとしても大丈夫なように、予め自分の財産の振り分けを始めている人たちがいるのです。
実はこの情報、やって意味がある人とかえって税負担が増えてしまう人がいるため注意しなければなりません。
相続発生時に相続財産が減っていれば、その分課税される税金は減りますので相続税の節税効果があるように思います。
しかしながら、相続はそんなに甘くありません。
というのも、仮に今から急いで贈与したとしても、3年以内に本人が死亡して相続が発生したら、生前贈与分もすべて相続税の課税対象になるのです。
それゆえ、早く生前贈与したからといって相続税負担を免れるわけではありません。
この話をすると、「それなら贈与税の基礎控除額である年間110万円以下の範囲でだけ贈与すればよいのでは?」と言われる方がいるのですが、残念ながら相続開始前3年以内の贈与財産については、贈与税の基礎控除額である110万円以下のものも含めて相続税の課税対象となります。
よって、節税という観点からすると慌てて今から生前贈与する行為にはあまり意味がありません。
自分の死後の相続に不安を感じているのであれば、慌てて贈与するよりも遺言書を書く方がおすすめです。
特にコロナウイルスは容体が急変してお亡くなりになるケースもあるようなので、もしものことを考えると元気なうちに書いておくことがとても重要になります。
遺言書に希望する遺産配分を記載しておけば、相続発生後のもめごとを防ぐことができます。
特に重要なのが、法定相続人以外への「遺贈」です。
遺言書がなくても法定相続人であれば財産を相続できますが、それ以外の人に遺産を残したいと思ったら必ず遺言書を書かないと取得させることができません。
このケースに特に当てはまるのが、「内縁関係」の方たちです。
内縁関係では婚姻関係は成立していないので、万が一どちらかが死亡しても一切遺産を相続することができません。
相続人として本人の父母や兄弟姉妹が出てくると、最悪の場合住む家を失う可能性もありえます。
このようなケースを回避するためには、遺言書によって一定の財産を遺贈するよう記載するか、亡くなる前に婚姻届を提出する必要があります。
遺言書は法的な効力のある書類ですが、実は家の中にあるものだけを使って作成することが可能で、専用の用紙などは必要ありません。
用意するものは以下3つだけです。
・紙(なんでもいい、便箋なども可能)
・ボールペン
・実印
印鑑は実印である必要はありませんが、信憑性を高めるためにも実印で捺印することをおすすめします。
これらを準備した上で、以下の事項を満たしていれば遺言書は有効に成立します。
・作成した日
・署名捺印
・一部を除いて直筆
このようにして作成した遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
相続税の節税という意味ではそこまで効果がない駆け込み贈与ですが、遺産分割という角度から見た場合に生前贈与が有効といえるケースもあります。
それは経営者の方です。
オーナー社長の場合、自社の株式の100%を自分で保有しています。
万が一死亡した場合は、株式が配偶者や子供たちに相続されるわけですが、一箇所に集約していた株式が分散してしまうと、会社の意思決定機能に支障が出ることがあるのです。
このようなケースでは、後継者と決めている子供にあらかじめ株式を贈与しておいたほうが、会社の経営体制を守れる可能性があります。
コロナウイルスの早期収束を願うばかりですが、もしもの時の対策をとることもとても大切です。
ただ、闇雲に動いてもかえってマイナスになってしまうので、各ご家庭にあった対策を考えることを心がけましょう。
この記事では110万円以下の贈与も3年以内のものであれば、相続財産に足されるようなことが書いていますが、必ずしも正しくありません。
足されるのは、基本的に、法定相続人だけなのです。
それゆえ、法定相続人ではないお孫さんやお子さんの配偶者への贈与は3年以内であっても足し戻されることはありませんので、相続税対策としては比較的容易で有効な方法です。
あとは、個人的には、紛失や改ざんのおそれがあり、要件を充たしておらず無効となる可能性のある『自筆証書遺言』よりは、多少費用はかかりますが『公正証書遺言』をお勧めします。
コロナ対策の生前贈与はかえって危険?について、どう思われましたか?
皇位の証しである「三種の神器」の贈与税は非課税に!
皇位の証しとして歴代天皇に受け継がれてきた「三種の神器」などは、皇室経済法で定められた「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」とされており、相続税の課税対象外になっているのです。
退位による生前贈与はこれまで想定されていなかったため、新たに設けられた皇室典範特例法の規定で、今回の皇位継承に限って贈与税を非課税とする措置がとられました。
宮内庁は、約600件を「由緒ある物」に指定しています。
三種の神器以外に、宮中祭祀(さいし)が行われる皇居・宮中三殿や歴代天皇の直筆の書などが含まれています。
2019年5月1日午前0時から新天皇陛下の持ち物となったのです。
今回、平成から令和になりましたが、テレビなどを見ていると、日本人として、やはり天皇は日本の象徴であり、必要であることを改めて感じました。
1年半ほど前に、大学院での授業の中で、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」は相続税の課税対象外なんですねということをおっしゃっていた生徒さんがいたので、相続税が非課税ということは知っていたのですが、当時調べると、贈与税は規定はないんだなぁと思った記憶があります。
ノーベル経済学賞の賞金だけが所得税が非課税になっていないのと同じような感じですね。
反対する方もおられるでしょうが、やはり天皇の存在は日本にとって欠かせないと思いますので、贈与税の非課税措置は当然かなと思いました。
元号が変わると諸々のコストが発生する企業や省庁などはあるかもしれませんが、それを避けたいのであれば西暦を使えば良いと思いますし、日常生活の中で、元号を使うのか西暦を使うのかという問題は、別個で考えれば良いと思います。
皇位の証しである「三種の神器」の贈与税は非課税であることについて、どう思われましたか?
東京国税局がオーストラリア当局と協力して滞納贈与税8億円を徴収!
日本国内で贈与税を滞納していたオーストラリア人男性について、東京国税局がオーストラリアの税務当局に税金の徴収共助を要請し、男性の預金から延滞税を含む約8億円を徴収したことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
オーストラリアの税務当局が男性の預金を差し押さえました。
日本の国税当局が租税条約に基づく徴収共助を要請した例は11件あるようですが、億単位の徴収は初めてで過去最高額となりました。
関係者によると、オーストラリア人男性は数年前、日本在住の親から数十億円の贈与を受けました。
しかしながら、男性は贈与税を納付せず、国税局の再三の催促に対しても拒否し、国税局は日本国内の男性の預金を差し押さえて一部を徴収しましたが、約8億円が未納となっていたため、国税庁を通じオーストラリアの税務当局に徴収共助を要請していました。
国をまたぐ個人や法人の資金の動きを探る場合、国税庁は租税条約に基づき海外の税務当局と情報交換できます。
滞納者の税徴収については、現在53の国・地域の税務当局に要請できます。
タックスヘイブン(租税回避地)での節税実態を暴いたパナマ文書問題では、各国の税務当局がグローバル経済に対応できていない実態が浮き彫りになっただけに、国税庁は海外に多額の資産を持つ富裕層の税逃れ対策を強化しています。
今回のケースのように、海外の税務当局との連携を深めているようです。
良いニュースですね。
悪質なものに対しては、厳格に対応してほしいです。
おそらく、表に出てきていないこのような滞納案件が結構あり、回収できていないものがそれなりにあるのではないかと思います。
こういうニュースが出れば、抑制になると思いますので、少なからず、滞留発生が減り、回収率も上がるでしょうね。
東京国税局がオーストラリア当局と協力して滞納贈与税8億円を徴収したことについて、どう思われましたか?