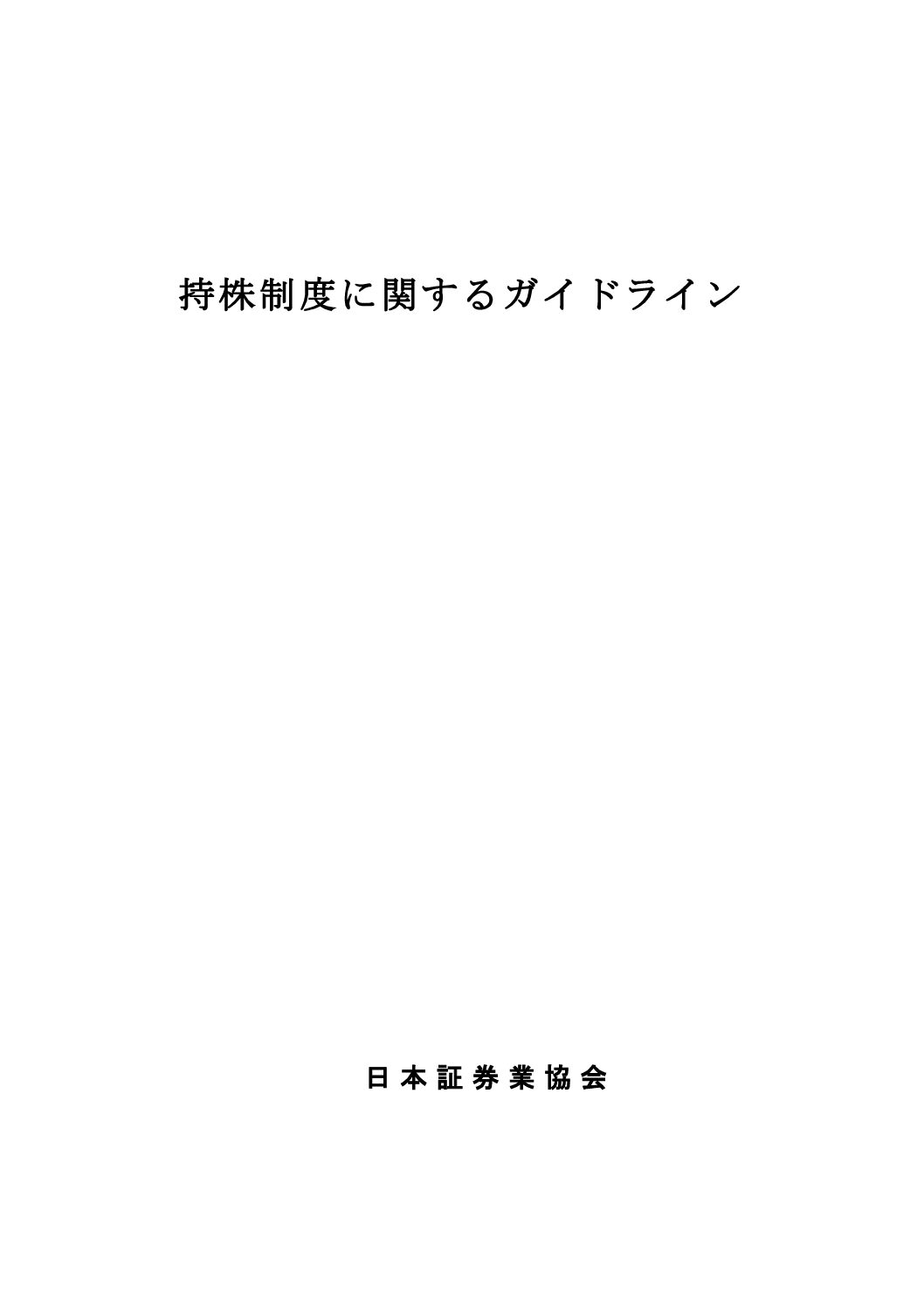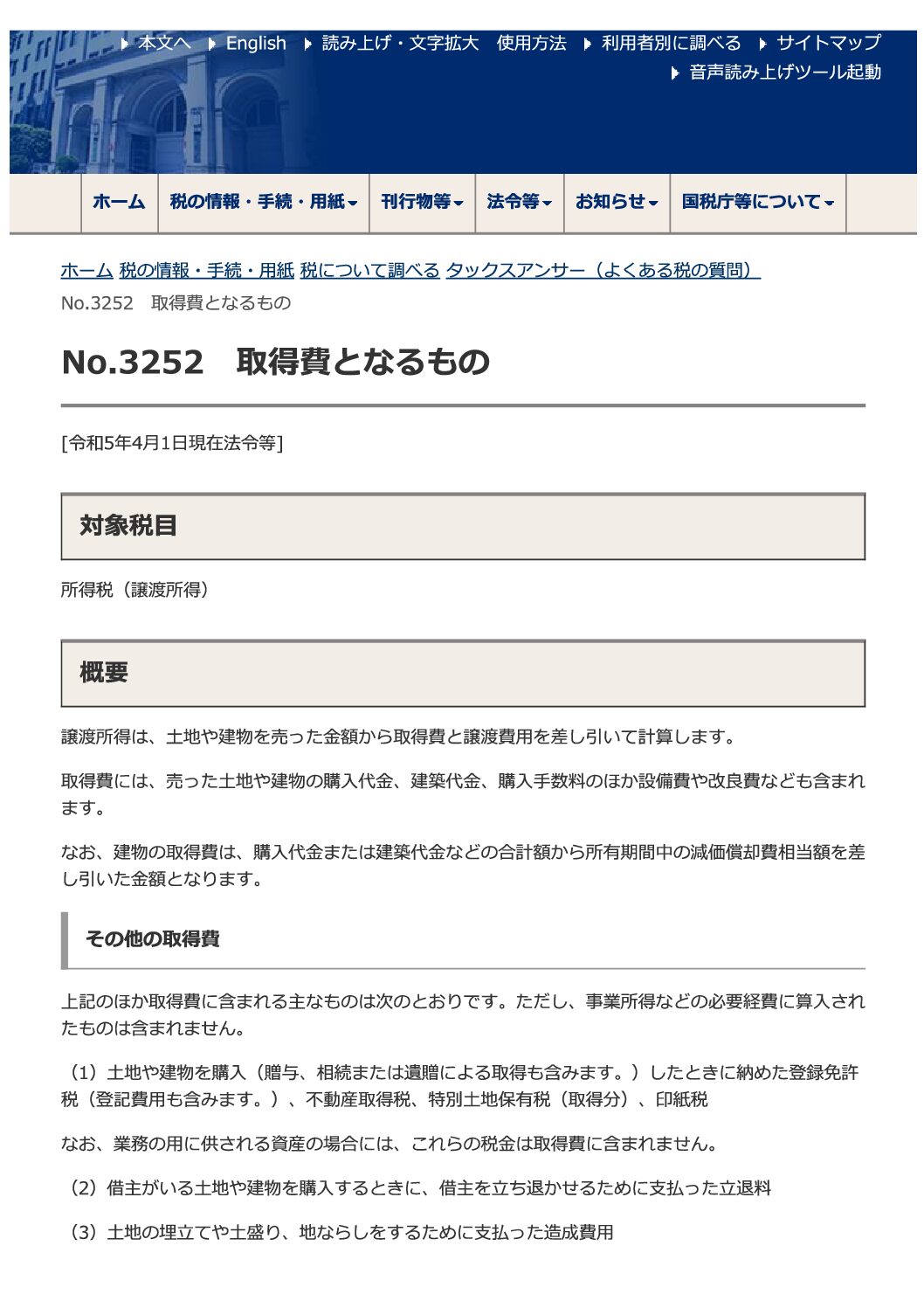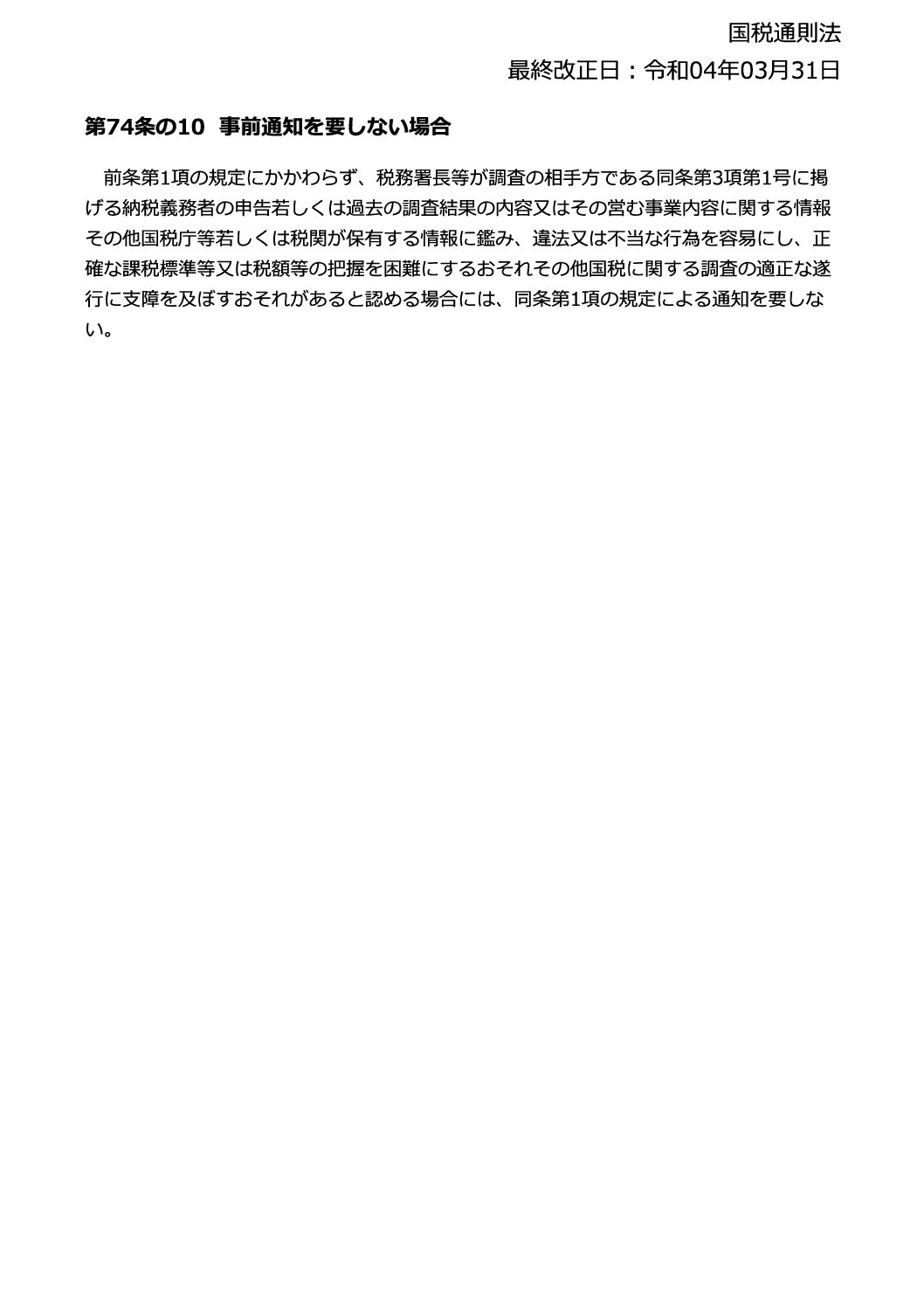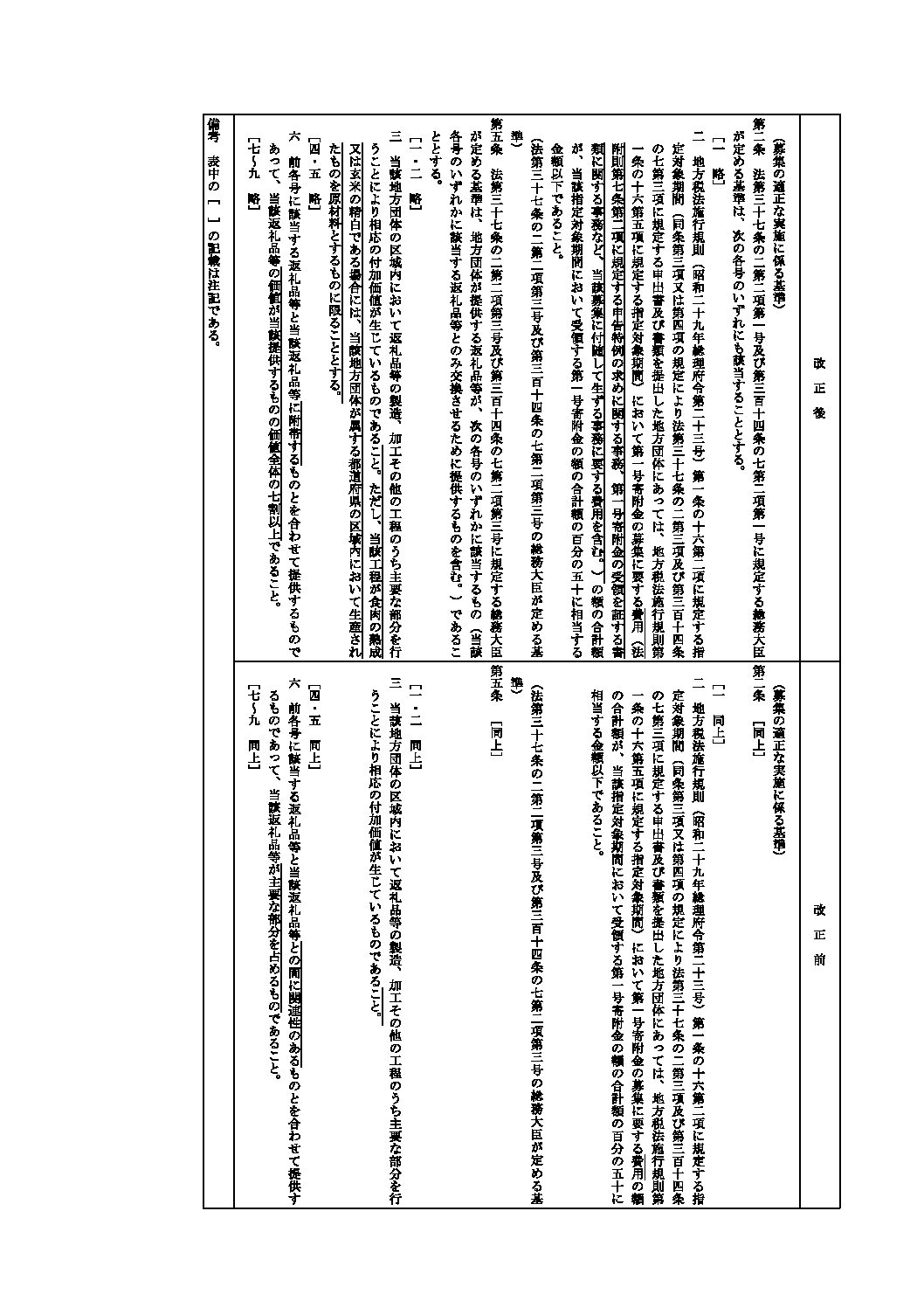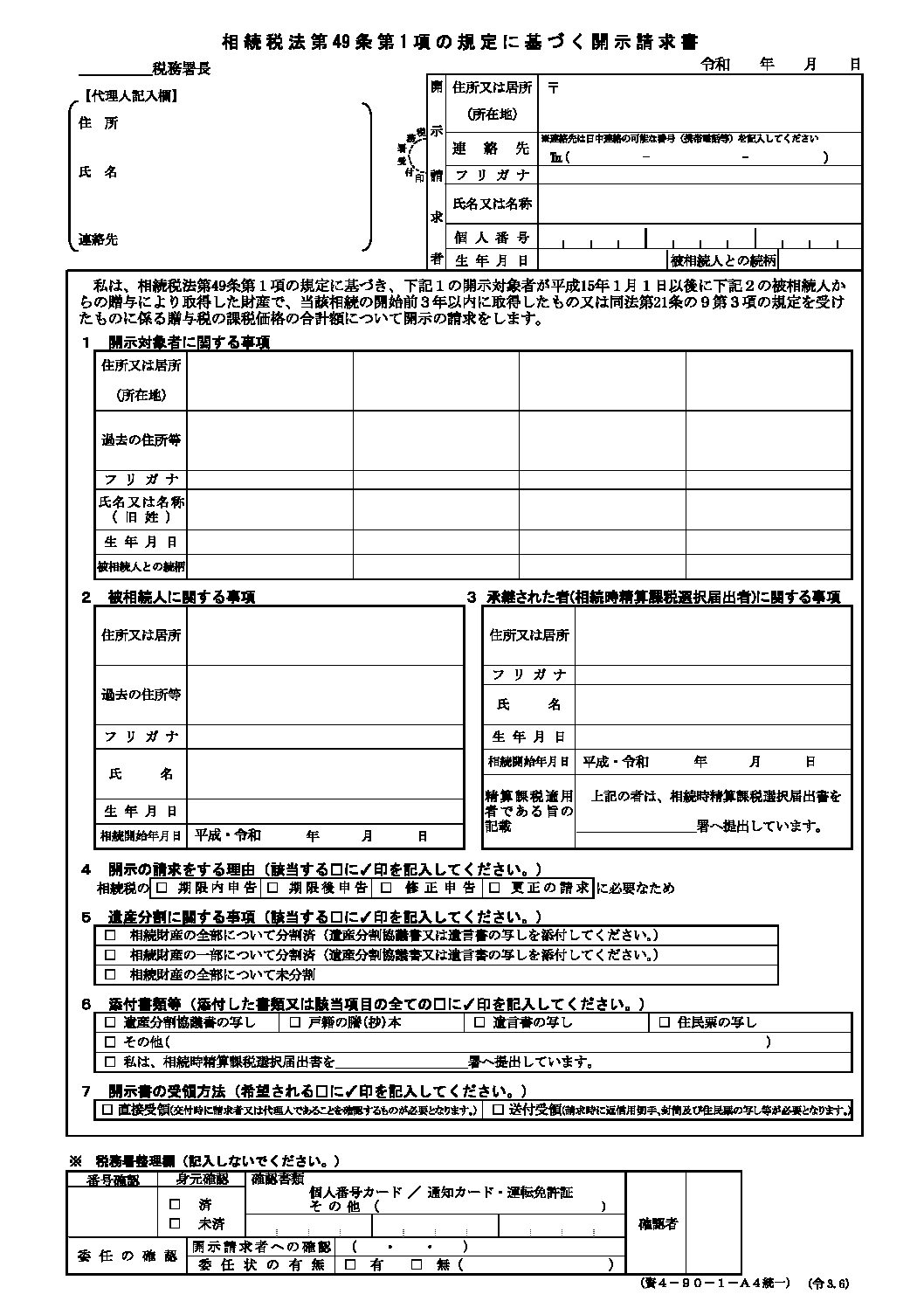事務所通信
2024年5月号『非上場会社でも従業員持株会を活用できる!』
『従業員持株会』という制度をご存じでしょうか?
聞いたこともない方もたくさんおられるでしょうし、知っていても上場会社で使われる制度と思われている方もおられるのではないでしょうか?
実は、非上場会社でも使えるのです。
そこで今回は、『非上場会社でも従業員持株会を活用できる!』について、書きたいと思います。
1.従業員持株会とは?
会社の従業員(当該会社の子会社の従業員を含む。)が、当該会社の株式の取得を目的として運営する組織をいいます。
2.従業員持株会のメリット
メリットとしては以下のようなものが挙げられます。
| <会社> |
| 従業員福利厚生制度の柱となる |
| 従業員に経営参加意識を持たせることができる |
| 株式の社外流出を防止できる |
| 株主からの買取要請に対処しやすい |
| オーナーの相続税対策に役立つ |
| <従業員> |
| 財産形成に役立つ |
3.従業員持株会のデメリット
一方、デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
| <会社> |
| 従業員の資本参加の度合いによってはオーナーの会社支配権が揺るぎかねない |
| 公正に運営が行われないと従業員から不満の声が出る |
| 退会等による換金の申し込みが集中すると株式転売の対応が難しくなる |
| 既存の従業員株主を持株会に吸収できないと株主管理に問題が残る |
| 配当が期待できないと従業員の不信感、不満が表面化し運営が困難になる |
| <従業員> |
| 倒産の場合、資産も失うことになる |
4.従業員持株会の設立形態
設立形態としては、以下の①から③が考えられますが、③民法上の組合として設立することが多いと考えられます。
| ① | 民法上の組合 |
| ② | 法人格のない社団 |
| ③ | 任意団体 |
③民法上の組合の特徴は以下のとおりです。
| 法的性格 | 民法667条の規定に基づく団体 |
| 法人格を持たない | |
| 税務上の
取り扱い |
法人税の課税なし |
| 会員個人が受ける | |
| 配当金は配当所得(配当控除可) | |
| 採 用 | ほとんどの会社で採用 |
5.従業員持株会の参加者
会社の正社員を参加者とするのが一般的だと考えられます。
なお、子会社の正社員も参加させることも可能です。
6.最後に
上場会社のみならず、非上場会社でも従業員持株会は使えます。
従業員に報いたいと考えていたり、相続税対策を考えている経営者の方は、検討してもよいかもしれません。
2024年5月28日 國村 年